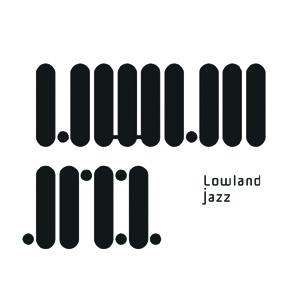人と人をつなげるもの ~研究、そして発信
― 拓児さんにとって、音楽とはなんですか?
山田「音楽そのものがなんであるのか? ということについては、考えても答えが見つからないので、置いておくとして、僕は音楽を仕事にして生活をしています。そこから考えると、音楽は『人と人をつなげてくれるもの』かな、と思います。例えば、ミュージシャン同士であれば、好きな音楽は共感できるツールだし、音楽を聴きにライブに来てくれたお客様であれば、その方の知っている曲を演奏することで、想い出を共有できるものでもあったりします」
― 明確でいらっしゃいますね。
山田「僕もたまに思うんです。なんで音楽やってるのかな? って。でもそれは、なんで毎日ご飯を食べるのかな? というのと同じで、音楽は僕にとって生活の一部です。ただ、音楽を研究するとなると、また気持ちが違うかな。と思います。僕も普段、音楽を勉強したり研究したりするんだけど、その時の音楽と、自分が出している音楽とは、またちょっと違います。例えば、研究のために作る料理と、食事の料理というのは違いますよね」
― そうですね。研究して本を出すのか、旬の素材を楽しむのか。目的によって違いますね。
山田「その勉強の成果として、演奏や表現があるんですけれどね」
― こういう距離感といいますか、バランス感覚が拓児さんらしいという感じがいたします。表現方法というのは多々ありますが、勉強し研究し、演奏者や観客と共感できることが音楽であるという。
山田「そこでつながるということが、非常に気持ちの良いことなんです。もちろん僕も一方的に発信することも大事だと思っています。評価を気にせず表現することも必要です」
― お仕事で使っていらっしゃる楽器について教えてください。日本のメーカーのサックスをお使いなんですね。
山田「はい。ヤナギサワというメーカーです」
― 型番はいつも同じものを愛用していらっしゃるんですか?
山田「はい。型番はA-9937です」
― ヤナギサワというメーカーのお名前、今回初めて知りました。
山田「サックスの世界3大メーカーはヤマハ、セルマー、ヤナギサワと言われています。その中ではヤナギサワのシェアが小さいんですが、アメリカのプレーヤーには好んで使われているようです。ヤマハは本当に大きな工場です。ヤナギサワは東京の下町にある町工場というか、びっくりするくらい小さいところで月に何百本か作り、世界に向けて出荷しているんです。ヤマハみたいに数は作れないけど、ヤナギサワは1台づつ懇切丁寧に作っている。という感じです」
― 目と手の届く範囲で職人さんが仕上げているサックスなんですね。
山田「そう。パートのおばちゃんが手作業ではんだ付けしてたりして、面白いんですよ」
― 海外のミュージシャンに愛用される名器なんですね。
山田「日本の町工場の技術が詰まっていて、確かなものです。現場に行くとわかるんですけれど、丁寧に、誇りを持って作っている。そこに居るだけで感動するっていうか、すごく面白いんです」
― 拓児さんの愛器のアジアゾウの彫刻もその工場で彫ってくれたんですか?
山田「そうです」
― お好きな映画、書籍、音楽がありましたら、教えてください。
山田「音楽で言うと、最近はバロック音楽。バッハとかですね。バッハを聞きます。僕はモーツァルトが大嫌いで、聞いているとすごく疲れるんです。なんていうか、うわーっとアイディアが攻めてきて(笑)。天才だとは思うんですけど」
― 比べて、バッハはどうしてお好きなんですか?
山田「なんでしょうね。僕は元々、数学が好きなせいもあるのか、幾何学模様が好きなせいか、ああいう幾何学な音楽が好きなんでしょう。メロディアスでもあるんですけど、数学的」
― 理数系のミュージシャン!
山田「数学がすごく良くできたわけじゃないんです。計算とかそういうのが好きだったんですよね」
― ミュージシャンにも色々なタイプがいらっしゃると思いますが、拓児さんは、感覚的に表現する部分と、研究して計算する部分のどちらもお持ちでいらっしゃるんですね。
山田「そこは、サックスの先生に言われたことなんです。右脳も左脳もどちらかが秀でてもダメ。バランスを保って行った方がいいよ。と言われました」
― 楽器を趣味としてだけではなく、プロとして演奏していく方には必要な気がいたします。
山田「うん。例えば音楽理論とか、知らなくてもいいことではあるんですけどね、特にJazzという音楽は理論を知らなくても感覚だけでやっていけるというイメージが強いんですが、思ったよりもJazzっていうのは、アカデミックなんです。尚且つ、それをあまり感じさせないように、音楽の一番大切なところ、踊りたくなるような楽しい部分を伝えていく。それには理論とか裏付けのある勉強をしている必要があるんです」
趣味は『象』? ~決め手は、インプットとアウトプットの上手な切り替え
― 遊びについて、お聞かせください。お休みの日は決まっていらっしゃいますか?
山田「いえ、全然不定期です」
― ライブが入ったら、その日がお仕事ですものね。お休みの日は何をして過ごしていらっしゃいますか?
山田「うーん。なんでしょうね。ものぐさというか、なんにもしないですかね(笑)」
― ご趣味は何ですか?
山田「動物園に行くことかな」
― 拓児さんの楽器にもWebサイトにも動物のモチーフがたくさん使われていますね
山田「そう、僕、象が好きなんです。ツアー先で空いている時間があったら、動物園に行きます。動物園と水族館は必ずチェックしています」
― 動物がお好きなのは小さいころからですか?何かきっかけがあれば教えてください。
山田「特に家でペットを飼っていたこともなかったし…。ある時、特に象が好きになって、象を求めてスリランカに行きました。スリランカの国立公園に象がいっぱいいるんですけれど、あ、僕の楽器に彫刻してある象も、その公園で写真に撮ってきたものを彫ってもらったんです」
― おお!この象はスリランカの象なんですか。拓児さんの公式Webサイトのお写真もそうですか?
山田「そうです。自分で撮影したものです」
― スリランカに行って象を見たんですか?それとも、象を見るためにスリランカへ行かれたんですか?
山田「目的の半分は象です(笑)」
― スリランカの象は特別なんですか?
山田「象にはアジアゾウとアフリカゾウというのがいて、性格が全く違うんです。アジアゾウというのは人と共存して生きてきた。アフリカゾウは象牙乱獲の問題もあって、人と闘いながら生きてきたので、アフリカゾウは非常に凶暴なんです」
― 人や荷物を運ぶインドゾウはアジアゾウですか?
山田「そうですね。アジアゾウは4つに分類されていて、その中のインドゾウです。他にスマトラゾウ、スリランカゾウ、ボルネオゾウというのがいます。もうちょっと細かく見ると、アフリカゾウの中に小さい種類のマルミミゾウというのがいて、それはすごく可愛いです」
― 素敵な趣味をお持ちですね!
山田「それから、動物以外で言うと、本当に最近なんですが、絵。特に何を描くということでもないんですけれど、絵の具でこう、遊ぶとすごくリフレッシュできます。新鮮な気持ちになります」
― 筆を使ってお描きになるんですか?
山田「そうです。パレットに絵の具を垂らしただけで、不思議と気持ちがリフレッシュして。絵は全然、下手なんですけれど(笑)。最近、子供が生まれて、その足形を取るために絵の具を買ったんですよ。あとは、子供の絵本。エリック・カールの『腹ペコあおむし』という絵本、ご存じですか?あの色がとっても綺麗で真似してみたりとか」
― もしかしたら、絵画の方面にも才能がおありかもしれませんね。
山田「それはないと思うんですけど(笑) 、でも、音楽でもそうなんですが、インプット・アウトプットということ。特別に意識はしないんですが、お腹が空いたときみたいに、今はすごくインプットしたい、勉強したいときと、アウトプットしたい、遊びたい、発散したいときというのがあるんですね。そういうスイッチが自然に切り替わるので、それに合わせて自分も上手く切り替えていける感じが、自分ではします」
― 行雲流水ですね。
山田「うん。絵を描きたいと思い立ったら、絵の具を出してきて、筆を使って。今は、その辺りがストレス解消にもなっているし、最近の新しい趣味です」
― 愛用している道具は決まっていますか?
山田「今は、100円ショップで全部揃うので、安いものを使っていたんですが、やっぱり、だんだんと良いものが欲しくなりますね。水彩画をやろうとしたら、紙の質が良くないといけないんですね」
― そこも拓児さんらしいですね。研究を重ねて良質のものを求めていかれるのはどの分野でも同じなんですね。

サックス奏者 山田拓児さん インタビュー 【1】 【2】 【3】 【4】