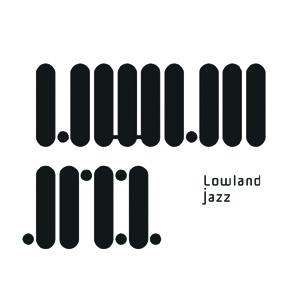養豚企業家のあゆみ ~世界をめぐり、2つの大きな決断の末に選び取った道。
― 経営者になられた当初は、お父様とご兄弟に支えられて、その後、北海道で養豚の第一人者になられる中岡社長ですが、その当時から、現在のように大きな規模での運営を目標にしていらっしゃったのですか?
中岡「これも人とのつながりでね。農業振興法(1969年)が出来たときに、国が小さい農家に対して農業と畜産の複合経営を勧めたんです。だから、北海道の養豚農家は昭和40年から50年の当時で24000件くらいありました。余市だけでも140から150件ありましたから。今は、道庁調べで全道に247件。厳しい状況を生き残ってきた企業です。ただ、生産頭数が減っているかというと、そうではない。吸収合併して大型化しているという現状です。」
― 熾烈な競争を勝ち残っていらっしゃったのですね。
中岡「結婚してから、事業拡大をしていくことになったのは、組合で先進地を視察するという機会があってね。当時、日本で一番、飼育頭数が多かったのは、茨木です。それから群馬、鹿児島、宮崎の順。私は大学で活字としては勉強したけれど、まだ実務からは離れたバリバリ元気の良い若者でした。本州の養豚専業施設を視察に行くと、経営のシステムや養豚業に対する新しい考え方が情報として入ってくるんです。バイクと自転車と犬で、という北海道の養豚業からしてみると、あちらの養豚の機械化された様子、ベンツに乗って迎えに来る養豚家達の新しい価値観がね、全く、まぶしいくらいでした」
― 当時は、北海道と本州の養豚業でそれほど大きな開きがあったんですか
中岡「そう。その違いを認識するようになって、努力する。こちらが努力すると生き物は答えを出しますから。人間と違ってね、手をかければ応えてくれる。そして、手をかけると同時に仲間が必要になるだろう。と思いました。ちょうど40年前になりますが、飼料販売店の声掛けで埼玉の大型養豚企業サイボクさんと交流する『サイボク親友会』の北海道支部の発起人になって、会を立ち上げたんです。百聞は一見に如かず。先進地との交流によって意識改革をされていくにしたがって、自分の経営の弱点が見えてきました。それを改善することを目標にやってきました」
― そうやって、今ある経営の形に近づいていらっしゃったのですね
中岡「今ある仁木農場へ移動してきたのは昭和63年(1988年)です。その辺りから、うちの経営規模も大きくなってきました。群馬の『グローバルピッグファーム』(以下、グローバル)というグループ経営で日本一の会社があって、その北海道での立ち上げをお手伝いすることになりました。このグループはアメリカやデンマーク式の農場設備を紹介し、あちらの獣医さんを採用してコンサルする会社として立ち上げしている会社ですから、世界的な情報が入ってくるんです。こちらの会社とも直接交流するようになりました。最初、代表の赤地先生にお会いしようと群馬の本社へ伺ったら、門前払いでね(笑)」
― ご自身で群馬まで訪ねて行って、門前払いされたんですか。
中岡「そう。塀の向こうで『先約があるし、会う必要ないから』って、言ってるのが聞こえてね。なんだ居るじゃねえか。そう思って、1週間後にまた訪問しました。連絡もしないでね。そうしたらまたダメ。また1週間待って、3回目。また行きました。そうしたら、『よく来たな。上がってこい』って」
― 三顧の礼。北海道からはるばる群馬へ。よく通われましたね。
中岡「赤地先生をはじめ、日本の養豚業界のトップが集まるグループです。養豚の価値や肉に対する責任、消費者に対する責任ということをそこで教わりながら、企業養豚というのは社会的責任を含めて、どうあるべきかということをそこで教わって、考えるようになりました」
― そうした出会いにによって、視野を広げていかれた。
中岡「グローバルの皆さんとアメリカ、オランダ、ドイツ、ベルギーと視察する中で、病気を出さない養豚というのが経営上非常に重要であるということがわかってきました。昭和57、58年~60年にかけて豚の伝染病が大流行して、非常に大きな損失を出したことがあったんです。その時、『イワタニ・ケンボロー』という会社から呉獣医という人が来てくれました。呉獣医は『病気が発生するということは、豚舎の日常生活環境や空調に問題があるのだろう』と言って、パンツ一丁で豚舎のスノコの上に寝てるんですよ。『何してんの?』って聞いたら、『豚と同じ体験をしないとわからないだろう?』って言うんです。面白い男だな! と思いましてね。その『イワタニ・ケンボロー』という会社は、アメリカのPICケンボローという品種の豚を日本で広めていた会社です」
― これまでの中岡社長が飼育していた品種とはまた違った品種ですか?
 中岡「SPF(※殺菌された飼育環境で育てられている豚。病気の原因となる菌を持たない) よりもレベルが高く、病気のない品種の豚を契約農家で育てて出荷するという方法で戦略的に業績を伸ばしている会社でした。北海道にもそういう農場を作ろうと虎視眈々としていたわけです。それまで自分達は、養豚は病気と共にある。という考え方でしたが、『イワタニ・ケンボロー』から、技術者が来たり、道外の養豚家が来て、病気が無ければ治療する時間も余計なビタミン、薬も必要ない。同じ頭数の飼育でも収益性が違う。と、盛んに説明されるわけです。収益を補償しますから、契約農家になってほしいというわけですよ。はて。どうしたもんか。」
中岡「SPF(※殺菌された飼育環境で育てられている豚。病気の原因となる菌を持たない) よりもレベルが高く、病気のない品種の豚を契約農家で育てて出荷するという方法で戦略的に業績を伸ばしている会社でした。北海道にもそういう農場を作ろうと虎視眈々としていたわけです。それまで自分達は、養豚は病気と共にある。という考え方でしたが、『イワタニ・ケンボロー』から、技術者が来たり、道外の養豚家が来て、病気が無ければ治療する時間も余計なビタミン、薬も必要ない。同じ頭数の飼育でも収益性が違う。と、盛んに説明されるわけです。収益を補償しますから、契約農家になってほしいというわけですよ。はて。どうしたもんか。」
― 迷われましたか。
中岡「かつて、自分からお願いに行った『グローバルピッグファーム』は北海道での立上げにも力を入れてくれて、組織を作って、随分、教育してくれましたからね。そこに義理人情があるじゃないですか。でも『イワタニ・ケンボロー』からも熱心に誘われて、病気の無いことによる収益性、供給の安定性という部分にも魅力がある。一週間くらい悩みましたけれども、最終的には、自分の養豚経営で進まざるを得ない道だと決心しました」
― それまでお世話になっていた組織のライバルに相当する『ケンボロー種』の飼育を決心なさったんですね。
中岡「北海道グローバル立ち上げの仲間だった『熊谷農場』までご挨拶に行きました。『病気のない養豚をやりたい。こういう決断をしたんで、何と言われても仕方ないけれど、グローバルを辞めてケンボロー農場の方へ行きます』と。グローバルは豚も餌も肉の販売も、全部グローバルのルートで行うことで組織の強化をしているんです。生産者は全てグローバルへ任せられるから、非常にありがたい。だけど、その組織から外へ出ると赤子の手みたいなもんです。それでも、病気のない養豚をやりたかった」
― 北海道グローバル立ち上げのメンバーは中岡さんが抜けることに対して、納得してくれましたか?
中岡「北海道中から『裏切り者!』と言われましてね。最初は袋叩きでした(笑)。ただ、その後は、全国の畜産会議なんかで、各地域のリーダーに会うと『どうだ? 上手くやってるか?』と声をかけてくれてね。無視されるようなことは無かったです。講演会を聴きに行ってもね、歓迎してもらいました。グローバルは実に素晴らしい組織です」
― 当時はケンボロー種を扱っている北海道の農場はひとつもなかったんですか?
中岡「なかった。完全に新しい農場ですからね。それまで事業拡大で移設する場合は、既存の豚を連れて行ったんですが、ケンボローの場合は持っていけるのは(自分の)体だけ。衛生管理のために、豚や機材はもちろん、鉛筆も服も全部ダメ」
― それまで育てていらっしゃった豚を全部処分したんですか?
中岡「そう、母豚も子豚も全部アウト。移設事業ということで国の助成も出ましたけど、建物建てるのに4億以上かかりましたし、豚の処分だけで6千万ほどかかりました。売れるものを売ったとしても叩き売りですよね。それで、新しい農場でスタートして、軌道に乗るまで1年半くらいくらいは無収入です」
― よく、ご決心なさいましたね!
中岡「良く決心したよね! ホント。そう思うわ(笑)。ただ、病気を持たないことの優位性、経営の安定化というのは、世界各地の農場を見にいって実感していることだったんです。ただ、それを自分達でやろうと思ったら、簡単にはできない。どうしても既存の疾病があるから。家族で手をかけて治療や予防をやっていても、気候の変化でどーんと病気が増えたりする。まあ、それが養豚の面白みでもあるんだけどね!」
カラフト犬と駆けた青春時代が決断させた、最先端の食品リサイクルシステム
― 新しい農場を1から始められて、その後は順調に進みましたか?
中岡「平成元年(1989年)に病気のない農場を取得してからは、企業として飛ぶ鳥を落とす勢いで成長しました。豚の飼育に関して、それまで200日かけて180kgくらいに成長していたものが、120~130日の豚で200kgに成長するんです。なぜかと言うと、健康だから。病気をしないからです。1kg成長させるのにエサが1kg違う。エサ代だけで1頭あたり2万円の経費削減ができたとして、それを1万頭で計算してみると、…そりゃあ、すごいよね!」
― 中岡社長が経営するビィクトリーポークでは、飼料に関して、食品リサイクルという方法を導入していらっしゃいますね。
中岡「平成21年(2019年)から道産飼料を自分たちで作っています。今、日本の穀物飼料は92~93%アメリカからの輸入に頼っていて、アメリカの天候や相場に価格を左右されてしまうんです。ところが、ヨーロッパへ視察に行くと、オランダのように日本と規模の変らない国が日本への輸出向けに豚肉を作っている。オランダでは社会インフラの中で出てくるタンパク源、例えば、製薬会社から出てくる培地用のタンパク質や、工場の食品残渣を一切ムダにせず、家畜の飼料にするシステムが確立しているんです。自国のエネルギーは少ないけれど、資料のコスト削減に徹底して利用することで、豚肉の輸出産業が安定化しているんです。向こうの生産者団体と交流をすると、『日本はまだアメリカのエサを買ってるのか?』と言われる。そのことが頭にあって、輸入穀物を減らすシステムで養豚をやりたいと思ったのがきっかけです。結果、道産飼料で育てたブランド豚の確立ということにもなりました」
― 海外で最新の現状を視察なさったことが、新しいシステムの導入につながったんですね。
中岡「平成21年に1万頭を増頭する時に飼料工場を作って、食品リサイクルのシステムを導入しました。自分が子供の頃は残飯を集めて飼料にしていたわけです。残飯回収は人の嫌がる仕事でしたが、そうやって育てた豚をみんな美味しいって食べているでしょう? そこにある種の反発心があってね。その経験があったから迷いなく、食品残渣回収のシステム化に踏み切れたんだと思います。それを知らない世代の養豚家にとっては、抵抗があるかもしれませんね」
― 実際に導入なさって、結果はいかがでしたか?
中岡「安定するまでは紆余曲折ありましたけれど、これによって、道産飼料で育てた道産豚ブランドを確立することができたので、販売に関しては大きな利点になりました。飼料効率に関しては、それまで2~3年かかりましたが、システムが確立してからは飼料コストが30%ほど下がっています」
― 道産飼料の原料になる食品残渣というのはどんなものを使用しているのですか?
中岡「先ずは、ジャガイモ。ポテトスナック工場から出るジャガイモの皮などの原料ロスや、ハネ品などの製品ロス。そして、牛乳のホエイ。それ以外にも、製菓工場からでる製品ロスも回収しています」
― 道外の養豚家との交流から始まり、海外視察を経て、常に最良のものを導入していらっしゃった結果として、北海道一の企業に成長した『ビィクトリーポーク』があるのですね。
中岡「イギリス視察の後にすぐ導入した『ウィンドウレス陽圧豚舎』(※窓のない豚舎で環境を完全管理できる豚舎)以外は、見聞きしてから10年、20年の経過の中で実現しました。各地で視察したことが、その時々で経営において重要な判断するときの基礎資料となっていったんだと思います。怖いもの知らずなんだよね(笑)。28~29の頃から始まって、どんどん外へ出て行きましたから。何度断られても、へこたれるという発想が無かったから(笑)」
中岡 勝 社長 インタビュー 【1】 【2】 【3】 【4】